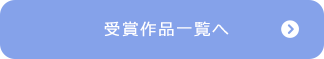【第1回】~ 妊娠・出産、新しい生命の誕生に接して ~
佳作
・九死に一生を得て
【一般部門】
佐藤 朗子
山形県 農業 65歳
昭和三十四年十二月から、三十五年正月にかけて、雪が少なく、大変凌ぎ易い日が続いていたが、四月、初産を予定している私にとって、実に有り難くない冬になってしまった。
粉雪舞い散る極寒の中で、裏山に登り芝を刈った。芝刈は炊木目的の他に、山の斜面を整地し、生まれて来る子の記念樹として、春、松の苗木を植えたいという強い思いがあり、ただ一心に働いた。その後、雪が積もり、私は炬燵に入って、産着やおむつ等を縫いお産に備えたが、三月の節句には、我家も改田ブームに乗り、外に出て働いていた。
初めて一輪車が購入され、まだ春浅い畑に、渡り板を敷いて土や暗渠の材料を運んだ。
こんな生活が臨月まで続き、とうとう体中に痛みを感じる様になった。急性関節リュウマチである。手足のふしぶしまでが痛み、食事中何度か、お膳の上に箸を置きながら食べたが、かむ度に顎の関節までが、カタカタと音をたてていた。
四月十一日夜、軽い腹痛があり、不安な夜を過したので、翌日早朝に、産婆さんに診ていただいた。産婆さんは、「もう少しだから、夜、早めに風呂さ入って、休ませでもらうどえ」と私に言い、母には決して入院させない様にと、きつく言い残して帰られた。
それから眠れない夜が一週間続き、私は、早くも疲れを感じていた。十七日午前九時頃、とうとう産婆さんに来ていただいた。産婆さんは、「あんまり早くから寝るもんでないよ、縁側でもふいでこいまず」と言われた。私は言われるまま動いてみたが、どうにも我慢出来ず、すぐ床についてしまった。
産婆さんは不満らしく、くどくど言いながら、私を診てくれておどろいていた。「なえだじぎに生まれんなだでこ、頭、覗えったんだもの、早くお湯沸かしてけろ」と言われた。
その言葉に家中が急にあわただしくなった。そして、産婆さんの指示で、生卵数個私の枕元に用意された。産婆さんは、更に激しい口調で、「生卵飲んで元気付けねどわがんねなだ」と私に言った。すっかりその気になった私は、激しい腹痛をくり返す度に、差し出される卵を、ただ飲み込んでいた。
卵は一つ又一つとなくなっていったが、とうとう体が受付けなくなり、陣痛微弱だというのである。十時半頃、夫は近くの内科医に行き、陣痛誘発剤を二回分もらって来た。産婆さんはそれを四回に分けて、一時間おきに、注射してくれた。
私はその後、頻繁に来る激しい陣痛にただ耐えていた。昼も過ぎ、やわらかい春の西日が窓を差していた。学生時代育児学の講義を受けていた私は、極限に来た事を知り、産婆さんに、二~三たずねてみたが、「あなたは、何でも知ってるから大なしだ」という返事だった。
家族が、代わるがわる心配し、「子供大丈夫だべが」「医者頼んでわりべが」とたずねた。大丈夫だ、大丈夫だ、これを何度かくり返し、とうとう夜七時を回った頃、母が、子供大丈夫だべがと問い返した。
産婆さんは、母のこの言葉を、さも待っていたかの様に、急にがっくりとうなだれ、低い声で、「だめだがしんね」と言った。母は「ほんじゃ母体は」と、続けて聞いた。「母体もだめだがしんねは…」と静かに答えた。
そこには、自信に満ちた先程までの産婆さんの姿はなく、心身共に疲れ果てた産婆さんが静かに頭を横に振っていた。この言葉に家族は蒼然となり、母は、産婆さん、「それでは医者呼ばせでおごやえな」といってすぐ町立病院に電話したが、折あしく、先生は不在で、婦人科医の研修会に出かけられたという事だった。
ついてない時は、本当についてないもので、どこに電話しても不在で隣町の婦人科医の老先生に、家族が無理にお願いして来ていただいた。時計はすでに夜の八時半をまわっていた。
産婆さんに、さじを投げられた私だが、なぜか不思議に冷静だった。昔、難産のため命を落としたという話しをよく聞いた事があるが、私もそうなるのかと一瞬思った。
二人の命は老先生と看護婦さんの腕にかかっていた。先生は長年のキャリアを生かし、速急に、迷わず、かんし分娩に入った。
カチャンカチャンと寝ている私の足元で音がし看護婦さんと息の合った手際よい処置がなされ、たちまち赤子がとり上げられ、まさに誕生のきせきだった。
私は約十一時間ぶりに陣痛から解放され、生きている事を実感していた。「男の赤ちゃんですよ」と先生の声、そういわれたものの、産声一つ聞こえないのである。
先生は、全身充血し、赤紫になった赤子の足首を持ち、高々と逆さに下げていたが、それでもなお、赤子は泣かなかった。私は一瞬息をのんだ。
更に先生が逆のまま背中を軽く二~三度たたき、ようやく弱々しい産声が、私の耳にかすかに聞こえた。蚊の泣き声にも似た我子誕生の第一声だった。
ああよくぞこれまで生きていてくれたものだ、親子で助かったのだと思うと感謝感激だった。涙がとめどなく溢れ頬をつたった。私はこの上ない幸せを感じ、この子が立派に成長するまで死んでなるものかと自分自身に強く言いきかせた。母親になった瞬間だった。
充血した赤子は、体はもちろん、顔中、痣の様である。七福神の中の寿老神の様に、長くくびれた頭に、産婆さんが脱脂綿で綿帽子を作り、かぶせてくれた。
「ごめんどうになってどうもおしようしなっし」顔中がこすれ、おせじにも可愛いとは言えない赤子を横に、私はみんなにお礼を言っていた。
小さな生命の誕生と、命を育て、育む事の出来る、女性である事の素晴らしさに、しばらくは感動が治まらず、興奮していた。
私の家族は、子供が生まれて五世代同居となり、家族年齢三百六十才の中で跡継ぎを生み、大任を果したという喜びと九死に一生を得た安堵感が、私を深い眠りにさそっていた。