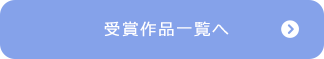【第11回】~ 赤ちゃんがくれるチカラ ~
入選
・生命のリレー
大阪府 主婦 女性 33歳
今年の夏、祖母の初盆のために少ない家族が集まった。自動販売機に飲み物を買いに出ただけでじりじりと腕が焼けるような暑い暑い日だった。今時珍しく祖母の家にはエアコンがないので六ケ月の息子は家の中に入った途端に額に汗を滲ませ、息子を抱いている私のTシャツもすぐにびしょ濡れになった。
「ほら、ばあさん、ひ孫がきたんやで、よう肥えてぱんぱんや」
父が線香に火をつけながら、仏壇に話しかけた。いつも祖母がお参りしていた仏壇に祖母の遺影が飾ってあるのを見たとき、私はああ、おばあちゃんは本当にこの世の人ではなくなってしまったんだなあと思った。
仏壇には遺影の他に祖母のスナップ写真が何枚も飾ってあった。どの写真も父が撮った写真でどの写真の祖母も笑顔だった。父は祖母が大好きだった。
祖母が不慮の事故で八十四年の人生を終えた二ヵ月後、私は息子を出産した。惜しかったね、残念やったね、楽しみにしてたやろうに。祖母の葬式の時、妊婦の私はいろんな人に声をかけられた。そういう言葉の類が一番胸に突き刺さった。二ヵ月だ。たった、二ヵ月。いつも助けてもらってばかりの私が唯一できる孝行がひ孫を見せることだったのに、それすらできなかった。最後まで駄目な孫だった。
でも、一番堪えていたのは父だ。父は祖母が亡くなる前と同じように明るく振舞っていたが、私以上にいろいろなことを後悔しているようだった。
祖母は堅実で頭がよくてユーモアのある人だった。そして昔の人、特融の我慢強さを持っていた。あれが欲しい、これが欲しいとわがままをいうこともなく、つらいことがあっても自分はじっと耐えて、いつも家族のことばかり気遣っていた。だから、みんなつい甘えすぎてしまったのだ。祖母の周りにはいつも人が集まり、私も何かあると祖母の家へふらりと遊びに行った。祖母とコーヒーを飲みながらなんでもない話をする時間が私にはとても大切だった。
祖母の不在が家族のエネルギーを静かに奪っていき、抗いようのない喪失感がみんなの心に広がり始めたころ、新しい命が生まれた。それは本当に小さい小さい命だったのに、あっという間に我が家を照らしたのだ。息子の誕生によって祖母の死はただこの世から消えてしまう「消滅」のようなものではなく、新しい命へ繋がる自然の摂理の一部となった。親から子へ、そして子からまたその子へ。ひとつの死があり、ひとつの誕生がある。命とは本来そういうふうに繋がれていくものなのだけれど、祖母を失ったショックが大きすぎて私たちは祖母の死をきちんと受け止めることができずにいた。息子の誕生は私たちに命の本来の姿を思い出させてくれたのだ。
妊娠中に祖母の家を訪ねたときの祖母の言葉をふと思い出す。
「あゆさん、母親は赤ちゃんを守っているつもりやけどなあ、ほんまは母親が赤ちゃんに守られてるんよ」
ふーん、そんなもんなのかあとそのときは深く考えもしなかったけど、今はその言葉の意味が痛いほどわかる。命のちから、子供のちからはすごい。ただ生まれてくるだけで家族を暗闇から救い出してくれたのだから。
お参りが済むと、みんなで近所のラーメン屋に向かった。
「ばあさん、ここのラーメン好きでなあ。食欲ない、ないっていいながら、結局、いつも全部食べるねん。ほんま抜け目ないばあさんやで」
父の話す、祖母の思い出話にみんなが盛り上がる。もし、息子が生まれてなかったら、こんなふうに笑えただろうかとつい考えてしまった。
父はすっかり元気になって今では孫馬鹿街道まっしぐらだ。祖母にそっくりなたれ目の息子は騒ぐ大人の横で逞しく寝息を立てている。ただ彼が息をしているだけで、みんながどれだけ幸せになれるのかなんて知りもせずに、眠りに落ちている。
正直なところ、今でもやっぱり後悔してしまう。そのたびに私は小さな命を抱きしめてその温かさに癒されるのだ。