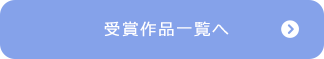【第11回】~ 赤ちゃんがくれるチカラ ~
入選
・命についた名前
愛知県 会社員 男性 45歳
六十の手習いだとばかり思っていた。仙台で暮らす父は、習字を始めていたらしい。私たち夫婦に第一子が生まれる、二年ほど前のことだ。確かに字を書くのが上手い部類ではなかった。
というよりも、下手だった。授業参観の親子作文などで、父が
ミミズが這ったような字を黒板に書くとクラスメートが大声を出して笑い、恥ずかしい思いをしたことを覚えている。当時の罪滅ぼしでもないのだろうが、教室通いで習い始めたのだと母から聞いた時にはいささか驚いた。余暇には庭いじりか草野球に興じるくらいで、趣味に習字を選ぶとは・・・。
誕生予定の報告に妻とともに実家へ顔を出した際、硯をするように、その理由をゆっくり話してくれた。
「・・・去りゆく人への手向けでもある名前をきれいに
書けないとは、情けない」
定年間際。父はある中小企業の人事部長を務め、異動などの辞令を受けた社員の名前を自筆で書く役割を担っていたのだという。
「栄転ならまだしも、リストラされる人間の名前もちゃんと
書けないようでは、なんだか、早く会社から去れって言ってる ような気がしてな・・・」
墨の匂いに包まれた居間で、父は自嘲気味に笑った。
一生のうち、人が字をきれいに書きたいと思うようになる
機会はどのくらいあるのだろうか。父は意を決して習字を
始めたのだった。
「まだ若いんだよな・・・。字が下手なのが申し訳なくてなぁ。
新たな境地で活躍してくれることを祈るだけだったよ」
私と妻は生まれくる命のことを切り出さなかったが、翌日の置手紙に妻が記していった。
『もうすぐ赤ちゃんが産まれます。
お名前、宜しくお願いいたします』
およそ半年後。家族が産気づいた妻の元に勢いいさんで駆けつけてくれたが、私たちの命は母親の胸にではなく、新生児特別室へと運ばれていた。
「充分な酸素が届いてないようで、蘇生処置を・・・」
医師の言葉に私は耳を疑い、皆の顔を見た。出生直後に産声はあげたものの、その後は泣かずで、場合によっては人工呼吸を要する酸素濃度不足の状態なのだという。体の一部が紫がかったようにも見えた。
呆然としている私に、父が問う。
「決めてあるのか?」
「いや、まだだよ。父さんに頼もうと・・・」
頷いただけで、待合室から静かに出て行った。
(どのくらい経ったのだろう・・・)
私たち家族はまんじりともせず、その場に固まっていた。
懸命な処置が施され、酸素不足が改善されはじめた頃、
何枚かの命名紙と筆を携えて戻ってきた父。
まだ予断は許されないと告げられると、初孫へ、窓越しにエールを送るかのように筆を動かし始める。一枚一枚、様子を伺いながら筆を進め、書き終えては紙を起こして保育器にいる赤ちゃんに見せるが、いっこうに反応がない。父が考えていたさまざまな
名前をなぞるも、時はいたずらに過ぎるばかり。袖を引こうとする母に「命を吹き込むんだ」と、父は強い口調で祈るように筆を持ち直す。
最後の一枚になった時、四方いっぱいに、はみ出さんばかりにその名が書かれた。はらいの勢いで墨が少し床に垂れると、小さな手が動き、私にはピンク色を帯びたように見えた。
「元気に、泣き始めましたよ!」
ドアを開け、助産師さんが待合室に駆け寄ってくる。
わが子が自発呼吸を始めたのだ。
命名紙に家族全員の嬉し涙。父の緊張感から放たれた汗が落ちると、その名は太くなり、力強く命が宿ったように見えた。
人間は世に出る際に命を授かり、そして名前を与えられるもの―
ベッドで待ちわびていた妻の両脇に、息子と「豪」と書かれた
命名紙がいびつな川の字のように並べられると、無限の力が
湧いてくる気がした。(終)