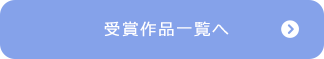【第2回】~ 赤ちゃんが教えてくれた喜び ~
佳作
・「ひとりが3人」
【一般部門】
吉本 夏枝
東京都 主婦 36歳
「わかりますか? これが戻した受精卵です。」
そう言われて覗き込んだモニターには、はっきりと認識出来るだけの特長に欠ける小さな塵のような白っぽい影がうっすらと映っているだけだった。
画面をなぞる医師の使い古されたペン先の行方を私は見落とさぬように必死で追いかける。今この瞬間に出来ることと言ったらそのくらいのことだけだろう。
私の胎内から採取された卵子と夫の精子を顕微鏡で人為的に受精させ、2日間培養した後再び子宮へ戻すというある意味自然の摂理に反したこの行為は、どこか懐かしい匂いのする午後の理科室の何かの実験にも似ていた。ビーカーの無機質で美しいガラスの表面を泳ぐ綺麗に細胞分裂した受精卵の姿を想像していた私にとって、はっきりしないモニター上の「影」は再び訪れることを半ば覚悟している絶望への入口のように思えて仕方なく、何とかその姿を見極めようとモノクロの目の荒い画像に必死で目をこらした。
顕微受精――活動率が極めて低い精子を針で卵子の中へ送り込んで受精させる。それはまさしく「神の領域」である。
専門書で探した病院がたまたま近所であることがそもそもの始まりだった。結局2年ほど通うことになるのだが、総体的な不妊治療の通院期間としては短い方だという。
カーテン1枚で仕切られただけの診察室までたどり着くのに待合室の簡素なイスで過ごす時間は時として3時間を超え、まわりで赤ちゃん用品のリースカタログを広げている妊婦たちを何人も見送っては溜息をもらした。診察はいたって簡単なもので、惰性になりつつある通院生活を止める勇気の持てない自分自身に正直呆れ始めていた。
そんな時、医師が真っ直ぐに私の目をみてこう言った。
「あなたの場合、自然妊娠はムリです」
診察室の窓の外を冬支度の鳥たちの群れが急ぎ足で飛び立って行く、どんよりとした曇り空の初冬の午後だったことを覚えている。
それから約半年後、私は診察台の上に乗っていた。一口に体外受精といっても、その準備期間は1月以上必要になる。講習会から始まり、排卵に基づいたスケジュール通りの投薬、10日前からの連日の筋肉注射、経過の確認、さまざまな術前検査と入院手続き。
けれどもこんなに時間のかかった本当の原因は「順番待ち」。 予約は6ヶ月先まで常に一杯の状態なのである。
前夜はさすがによく眠れなかった。やっと来たという気持ちと、とうとう来てしまったという対照的なふたつの気持ちの間で夜通し揺れ続けていた。ようやくウトウトしかけた時、枕元の目覚まし時計が嘲るようにけたたましく鳴り出した。
2日前に採卵した時のことは麻酔で朦朧としていたせいもあって、うっすらとした意識の中で若い看護婦さんがずっと手を握り締めていてくれたことだけしか覚えていない。
急なお産があったようで予定時刻よりだいぶ遅れて医師が到着した。1度だけ外来で診てもらったことのある女医さんだった。やりとりがこれでもかというくらい事務的且つスピーディで、正直好印象だったとは言い難い。ここが大学病院である以上、ひとりの担当医師がずっと携ってくれるというシステムではないことはわかっているつもりだったものの、下着を外しベッドに横になりながら、この期に及びながらも萎んでゆきそうになる自分自身を必死で抑え込んでいた。
手馴れた様子で準備が始まった。いよいよ私が「患者」ではなく「実験材料」になる瞬間が来る。たったひとつ特別なことがあるとすれば、私自身がその実験を切望したということだけだろう。
結果までは2週間。
yesかnoか、答えはどちらかひとつしかない。自分の中の可能性を信じるよりも、悪い方へ向かうことばかりを思い描き、先回りの諦めモードでショックを最小限に抑える防衛策を知らず知らずのうちにとっていた。
自分の弱さを痛感するばかりの日々。
ユニセフや災害募金のポスターに映る子供たちの姿ばかりが目に焼き付いて、自己満足と知りながらも募金をした。
神の領域に踏み込もうとする行為、もしかしたら自分はとんでもないことをしているのではないのか――今更ながらの自問自答で、発展性のない朝を毎日のように迎え続けた。
2週間後。
何も考えないように。何も求めないように。
その頃になると、私の中に奇妙な静けさが横たわっていた。
そして……
生まれて初めて、「神」の存在を感じた。
私は自分の中に小さな命を育み始めたのである。
それからおよそ1年と3ヶ月。私のベビー達は色々な人々の手を借りてすくすくと育っている。精神的にまだまだ未熟な私の腕の中には、甘えん坊の男の子と、ちょっと太めの女の子。そう、私は男女の双子を授かったのである。
何かを創り出すということは難しい。
ましてや「人間」をこの手で育んでゆくことの大変さは、想像を絶するものがある。
ひとときも離れることなく共に生活している彼と彼女に、私は何を伝えられるだろう。ある意味私の身勝手でこの世に生を受ける形となった幼い兄妹を、私はどれだけ幸せにしてあげられるのだろうか。
疲労や睡眠不足や不安や責任の重さで押し潰されそうになることもある。そんな時は、忘れかけていたひとりぼっちのあの頃の自分を思い出し、私のために生まれてきてくれたふたりを思いきり抱き締め、その初々しく危なげな「存在」を手足をバタバタさせるまで存分に確かめてみるのである。
泣く。笑う。グズる。食べる。眠る。
毎日ふたり分の笑顔とおムツ、そして離乳食作りに奮闘しながら、今までの人生の中で初めて人から心底頼られている自分というものを感じている。嬉しいような、悲しいような、複雑な心境である。
そして今思うこと。
私の中の・命・が3つに分かれ、個々としてそれぞれの成長を遂げて行く――味わったことの無いほどのこの幸せを、関わってくれた全ての人々に感謝すると共に、同じ症状で悩むたくさんの女性たちが、偏見や苦痛や経済的事情に負けることなく、数多くの・チャンス・恵まれることを祈ってやまない。